悩みが消える「ダメだしノート DDNプロジェクト」
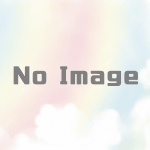
これは苦手な人間関係についてノートにダメ出ししていくことで客観視していき、対処法を考えるなどして、人間関係を改善することができるようになる本です。
「ノートに書く」はたいてい上手くいく私は

悩まないためには自分を知ること「超客観力 DaiGo」
Amazonのサイトへ 自分がわからないと自分に合わないことをやり続けてしまう この本は自 ...

腸がもつ不思議な力「腸と脳 エムラン・メイヤー」
腸と脳は連携している この本は腸と脳が相互に連携していて、直感的判断、情動、ひいては脳疾患 ...

自分の使命を見つける方法「パッションの見つけ方」人生100年ずっと幸せの最強ルール ボーク重子
パッションとは それがなければ自分ではないと感じるもの。人生の使命のようなものです。 自分 ...